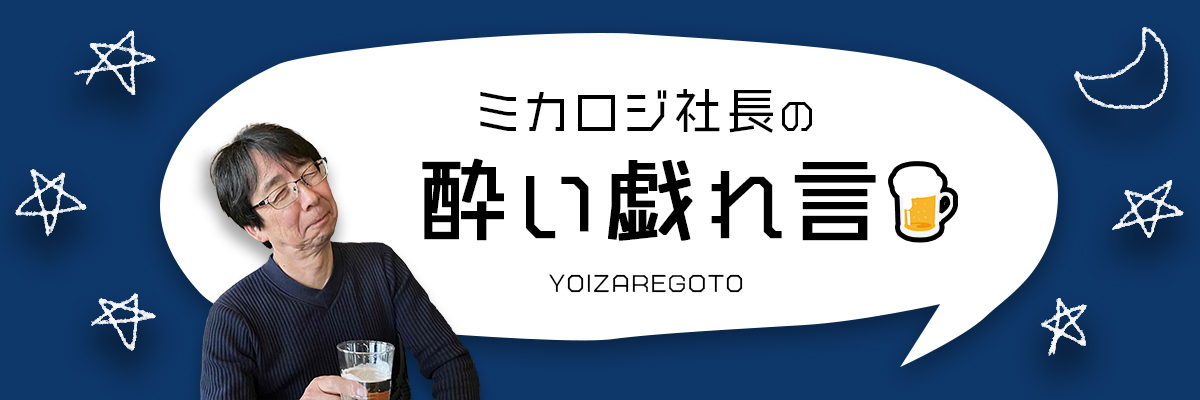NO.663【「なるほど」の感覚に軸足を置く】
他社と似通った製品を作っていては、いつ価格競争に巻き込まれかねない。
生活者の不満を見つけて解消する「なるほど」の感覚に軸足を置いてくことで
他社と横並びになりやすい商品は避け、確実に利益を出し続ける。
アイリスオーヤマの会長さんが話されていました。
毎週月曜日のアイデア会議は有名ですよね。
ミカロジは中小企業、物流サービス、BtoBなのでアイリスオーヤマさんとの
経営スタイルはまったく違いますが、「なるほど」の感覚に軸足を置く
という考え方は参考になります。
どんなビジネスにせよ、他社と横並びの
価格競争では生き残りが難しいでしょう。
ですので、物流サービスにおける
顧客の「なるほど」を見つけるのは簡単ではありませんが、利益の出ない
価格競争で疲弊することを考えれば、たとえ難しくとも顧客の「なるほど」を
追求することに精を出していきます。
「あっ、ちょっと浮かんだ!」でも、今はまだ秘密です、、
NO.662【嫉妬の世界に身を置かなったのは幸せなこと】
「嫉妬」。
出世競争の中に生きる男が持つ、最も醜い感情のひとつ。
同期の陰口を叩く、悪意のある噂話を流す、実務の足を引っ張る。
そして相手が出世コースを外れていくまで、それらの行為を飽くまで続ける。
ある意味、女の嫉妬より陰湿で始末が悪い。
このご時世、男だ女だはご法度でしょうが、実際に大きな企業ほど
このドロドロした嫉妬の世界はあるのでしょう。
私の場合、元々出世欲はなかったし、誰にでも合わせられる調子の良さを
持ち合わせたおかげで、この嫉妬の世界に身を置くことはありませんでした。
ある意味これはこれで幸せなのかもしれません。
毎日を陰口・噂話・足の引っ張り合いで過ごすなんて、
頭がおかしくなりそうですよね
NO.661【大将は好かれているようで憎まれている】
大将というものは、家臣から敬われているようでたえず落ち度を探されており、
恐れられているようで侮られ、親しまれているようで疎んじられ、
好かれているようで憎まれているものよ。
徳川家康の言葉だそうです。
これを私に当てはめてみますと、敬われることはないだろうし、
恐れられてもいないだろうとは思っていましたが、疎んじられたり
憎まれているのだと思うとちょっと寂しい気持ちになりました。
しかし大将と家臣、社長と部下、時代は違えど、上下の関係で
あまり親しくなってもいけないのかもしれません。
ふと、疎んじられているのでは?に心当たりが出てきました、、、
NO.660【名前間違い見るその人の資質】
菊地と菊池、三沢と三澤、井出と井手、川野と河野
百歩譲ってこの手の名前間違いはあると思います。
しかし私の見角(ミカド)。
めったにない名前ですので、間違いにくいと思いきや
「三角」とメール文章などに書いてくる人が一定数います。
慣れているので「またか」程度にしか思いませんが、
自分から売り込んできた営業マンに快く接したときに
「三角」で来られた時には、「資質が低いので、付き合うのはやめよう」
つい思ってしまいます。
こういう経験踏まえ、相手の名前間違いは失礼と自分自身も肝に銘じ
菊地と菊池など間違いやすい名前の時ほど注意しようと心掛けています。
しかし三角じゃないよ見角だよ、3回伝えても三角で来た人とは
絶交しました。
NO.659【選挙時の政治家とノルマのきつい営業マン】
選挙が始まると必ずと言っていいほど街宣車から
「私を勝たせて下さい」「私を助けて下さい」
連呼が聞こえてきます。
この文言にはいつも自己中心だなぁと違和感を抱いています。
と同時に
「ウチの商品買って下さい」「ノルマに協力して下さい」
という営業マンの営業トークにも通じるものを感じてしまいます。
結局どちらも国民や顧客を見ていません。
まあ営業マンは会社や上司の圧力なので仕方ない部分もありますが、
政治家先生たちはもう少し気の利いたセリフを考えた方がいいのでは?
とか言って、私がもし選挙に出たら、「
何がなんでも勝たせて下さい!」
土下座までするかもしれません、、
NO.658【アイデアキラーの撲滅】
無理・無駄・前例がないといった言葉は禁句。
「アイデアキラーの撲滅」つまり考えを殺すような言葉を使わないよう徹底。
マクドナルドさんの企業風土だそうです。
こういう企業風土なら、誰もが自由に自分の意見を入れるのでしょう。
ミカロジ経営理念「楽しく働く!」
この理念実現にも「アイデアキラーの撲滅」は大きな力になるでしょう。
早速ミカロジでも取り入れたいと思いますが、先ずはトップである私が
部下たちのアイデアや考えを殺さないようにしなければなりません。
口が軽い私ですので、ついうっかり「そりゃダメだ」言ってしまいそう。
ですがせっかく「アイデアキラーの撲滅」という参考になる取り組みに
出会ったのですから、私の口にガムテープを貼ってでも実現したいと思います。
NO.657【行き詰まったら、自虐的な発想をしてみる】
「中小企業様専門の物流会社です」「物流を楽にして、本業に集中しませんか」
「御社の物流部としてご利用下さい」「女性が運営する物流会社です」
中小企業でもキャッチコピーは大切と考えていますので、
日々顧客に刺さるキャッチコピーを考えています。
ですが、キャッチコピーのネタに行き詰まること多々あります。
そんなとき、「史上最低の遊園地」「まずい、もう一杯」「セガなんてだせえよな」
こんな感じの自虐ネタを考えるようにしています。
常にミカロジをよく見せようとすると思考が袋小路に入ってしまいますので、
あえて真逆の自虐ネタの思考にすることも一つの考えたと捉えています。
ただ「史上最低」「物流がひどい」「ミカロジなんてだせえよな」
というキャッチを出す勇気がでてきません、、、
NO.656【「潰れるかと思った」経験が会社を強くする】
「潰れるかと思った」
100円ショップダイソーの社長さんは、
急激に円安に振れた22年を振り返りました。
更に「円安がなければここまでできていなかった。円安があって強くなった」
経営者に於いては、誰もが「潰れるかと思った」経験はしたくないでしょうが
私含め多くの経営者は「潰れるかと思った」経験をしているでしょう。
問題はその先で、「潰れるかと思った」経験をダイソー社長さんのように
如何に会社を強くすることができるか?
ここが良い経営者と悪い経営者の
差なのかもしれません。
私も5期連続赤字の「潰れるかと思った」経験。
その後会社を強くすることができたかどうかはわかりかねますが、
せっかく苦しんだ経験ですので、これからもその経験を生かして
会社を強くすることに邁進していきます!
NO.655【上を向いて進んで、下を向いて暮らせ】
「進むときは上を向いて進め。暮らすときは下を向いて暮らせ。」
仕事においては目標を高く置き、より高みを目指すことは大切。
ところが上ばかり向いていると、過信したり自惚れたりすることに気づかない。
だから日常生活は質素を心掛ける。
こんな文言に出会いました。
ちょっと儲かるとすぐ派手な生活をする社長さんを数多見てきました。
かくいう私も創業そうそうすぐに一人で数億円を上げてしまいましたので
有頂天になっているときがありました。
私レベルですが贅沢もし始めました。
今思い返せば、穴があったら入りたい心境です。
この文言の通りに、上を向いて進んで、下を向いて暮らすことは
経営者にとっても大事なことでしょう。
幸い(?)私には悪戦苦闘期という
地獄の苦しみを味わっていますので、贅沢をしたらまたあの苦しみをという
恐怖心が植えついていますので、ただひたすら質素な生活で上を目指します!
NO.654【餅は餅屋じゃなくなってる】
「餅は餅屋」という諺があります。
餅は餅屋がついたものが一番うまい。
その道のことは専門家が一番という例えです。
ところがビジネスにおいては、この諺が通じない場合があるようです。
先日の新聞記事で、人材コンサル企業が、自社の人材育成につまずき
倒産と出ていました。
この記事読んで「おいおい、、」
それ以外にも営業代行企業が自社の営業できない、コンサル企業の経営不振など
「餅は餅屋」じゃなくなってる事象がビジネス界に於いては多々あります。
笑うに笑えないことかもしれません。
などと呑気に言ってる物流会社のミカロジも、素人がやってる物流サービスと
言われないよう「物流サービスならミカロジ」になるよう日々研鑽します。