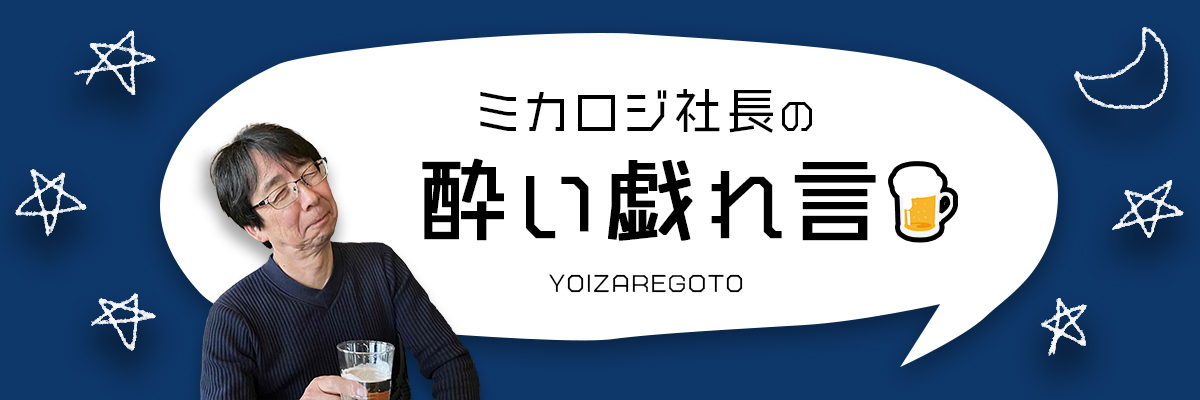NO.623【業績が先か働きがいが先か】
「業績が伸びたから働きがいが高まった」のではなく、
「働きがいの高まる取り組みを続けたから業績が伸びた」
「働きがいのある会社」ランキングトップ6年連続の企業社長談。
こういう考え方はミカロジ理念「楽しく働く!」に通じるものがあります。
まあ私の場合は、このランキングを意識したわけではなく、
私の拙い経営で多くの人に嫌な思いをさせて会社を去らせてしまったので、
その反省を踏まえて楽しく働く会社を作ろうという考えに至りました。
今現在ミカロジが働きがいのある会社かどうかはわかりませんが、
働きがいがあって業績が伸びる会社を目指して、今日も頑張ります!
NO.622【独断すれども独裁せず】
幅広い部下の意見に耳を傾けて最終的に自分だけで決めるのが独断で
意見を聞く姿勢を持たないのが独裁。独裁が良くないのは言うまでもないが、
多数決で他人に判断を任せるのも良くない。更に独断して、その結果に責任を
負うのが社長の仕事。
このようにして文章にして読むと当たり前だなぁと思うのですが、
世の中まだまだ独裁的な経営者は多いですし、2代目経営者や
サラリーマン経営者には他人任せの経営者も散見されます。
と偉そうに言う私はどうかというと、独裁も他人任せも両方併せ持つ
ある意味一番ダメな経営者のような気がしてなりません。
ではどうすればと考えても妙案は浮かびませんが、せめて結果に責任を
持つことだけは心掛けたいと思います。
NO.621【競合他社とのベンチマーキングは行わない】
ブルーオーシャン企業は、競合他社とのベンチマーキングは行わず、
従来とは違う戦略ロジックに従っていた。買い手や自社にとっての
価値を大幅に高め、競争のない未知の市場空間を開拓することによって
競争を無意味にしていく。
鈴木敏文氏が率いてる頃のセブンイレブンが正にそうでした。
鈴木氏は他のコンビニをいっさい見に行かなかったそうです。
単純な私は早速これを取り入れ、同業者を見に行くことは極力控え
如何にレッドオーシャン市場から距離を置き、新たな顧客のニーズを
探し当てるかに尽力できるか?と日々研鑽しています。
と言うと格好いいですが、まだ到底その域には達していません。
ですが、これからの中小企業の生き残りには、先ずは競合他社との
ベンチマーキングは行わないという視点は欠かせないのではないでしょうか。
NO.620【数字よりも大事なもの】
経営において数字は大事である。だがそこに働く従業員がいる以上、
数字よりも大事なものが経営にはある。それを大事にすれば数字は
あとからついてくる。と何かに書いてありました。
捉え方は違うかもしれませんが、数字が苦手な私にとっては良い表現です。
かといって、それがなにかは私ごときに分かりかねますが、
あえてミカロジで当て嵌めますと「楽しく働く!」ではないかと考えます。
みんなが楽しく働く環境を作りながら、業績が良くなる戦略を実践する。
これが私に課せられた数字よりも大事なものと肝に銘じ、と同時に
数字嫌いを克服することもしていかなければなりません。
後者の方が大変だったりして、、
NO.619【火種運動を起こそう】
一人一人が胸の中の火種を火がついていない者に移してくれ。
その火種をまた別の者に移せ。私も率先して火種になる。
火種運動を起こそう。そうすれば今は灰のような米沢藩も
きっと燃え上がる。と見事改革に成功した上杉鷹山。
好きな話です。
鷹山は米沢藩主についた時はまだ若く、外様だったこともあり
中々受け入れられなかった。それでも若手の中で鷹山を慕う
数名の者たちにこの火種を移していきました。
買収当時、ほぼ全員から反発を喰らいました。
ですがパートさんの中で数名、私を支持してくれる人がいましたので
この火種の話を胸に秘めながら、今は灰のようなミカロジも
きっと燃え上がると信じて、ここまでやってきました。
見事ミカロジは!とまで言えませんが、当時よりは燃えていると思います。
火種を移してくれたみんなに感謝です!
NO.618【新たな営業手法を模索中】
ある日終日社内に居ましたので、どれだけ営業が来るか見てみました。
結果、メールDM64通、テレアポ7件、飛び込み2社でした。
どの業界、どの会社も必死に営業していることが見て取れました。
「大変だなぁ」と思う反面ミカロジも他人ごとではありません。
今まではFAX-DM中心に集客をしていましたが、最近問い合せ率が
メッキリと減ってきました。ですのでメールDMがいいのか
テレアポや飛び込みがいいのかわかりませんが、ミカロジも新たな
手法で営業していかなければなりません。
といってもどの手法も先駆者がいて成果を出すのは大変でしょう。
なんか誰も気づいていなくてメチャクチャ成果出る営業手法ないかなぁ?
NO.617【顧客にとっての価値はなにか?】
ある土木重機用オイルメーカーが「顧客にとっての価値はなにか?」
を分析して得た答えは土木重機の稼働率だった。
土木会社にとっては一時間の故障が一年分のオイル代に相当した。
そこでこのメーカーは、重機の稼働率を保証することにした。
今では土木会社はオイルの元値さえ聞かなくなった。
この「顧客にとっての価値はなにか?」は大切な問いですね。
つい私たちは、自分たちの価値を考えてしまいがちです。
そうではなく、先ずは徹底的に「顧客にとっての価値はなにか?」を考える。
そうでなければこのオイルメーカーのように稼働率の保証という
発想は出てこないでしょう。ただその考えた結果が、
価格交渉すら不要になったというメリットがついてきました。
常に私も頭の中は、ミカロジの価値は?で埋め尽くされていましたが
ここは早々に切り替え、「顧客にとっての価値はなにか?」
モードにしていきます。
NO.616【適材適所は経営戦略に勝る】
「適材適所は経営戦略に勝る」
こんな文言を目にしました。
う~ん、経営戦略は大事だと必死に学んできたつもりでしたが
適材適所の方が上か~と、中々受け入れられない文言ですが
一面そうなのかもしれません。
そういえば「ビジョナリーカンパニー2」というビジネス書の中にも
誰をバスに乗せて、誰をバスから降ろすか。更に乗せた人には
適切な椅子に座らせる。そうすれば目的地にまでスムーズに行ける。
裏覚えなので合っているかわかりませんが、こんなことが
書いてあった記憶があります。
ですので、受け入れられないと心を閉じるのではなく
経営戦略は勉強しつつ、適材適所もしっかりミカロジに当て嵌めていきます。
でも実はミカロジ従業員、すでに適材適所だったりして、、
私の自慢癖が出てしまいました。
NO.615【社内の専門用語はダメ】
「メガヘルツ」と「速度」。「水温」と「温かい湯」
買い手が理解し、評価してくれそうな言葉を使っているか?
それとも社内の専門用語をそのまま充てているか?
後者であれば顧客の理解を得られるのは難しい。
まさしくその通り!だと思います。
最近マーケティング強化でその手の会社さんと打ち合わせしますが
「リード」「ナーチャリング」「コンバージョン」と
彼らの社内の専門用語だらけです。
せっかく「おっ、このサービス良さそう!」と思っても
話を聞いているうちに「ナーチャリング」という言葉で
一気に気持ちが萎えてしまいます。
と他社批判でなく、ミカロジでも社内や物流の専門用語で
お客さんと話していないか、再点検したいと思います。
NO.614【固定観念を払拭する】
「経営スキルはこれから学べばいい。周りが分担して足りない部分を
埋めることができる。でも信頼できる人間でなければ人はついてこない。
若さも後から手に入れることはできない。」と50歳を前にした社長が
22歳の女性に社長をバトンタッチという記事を目にしました。
50歳前では私より10歳近く若い社長です。ビックリしました。
私的にこの社長と似たような考えを持ってたつもりですが、
それでもバトンタッチは私が65歳ぐらいだと漠然と思っていました。
ましてやバトンタッチは22歳の女性です。
よっぽど優秀なのでしょうが、それでもまだ22歳です。
と思ってしまうことが、私が固定観念に囚われているのかもしれません。
ですので、この記事をきっかけに先ずは私の固定観念の払拭から
初めて見たいと思います。
それでも22歳だもんなぁ、、